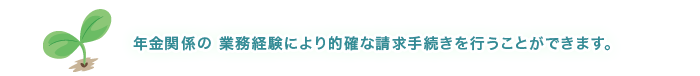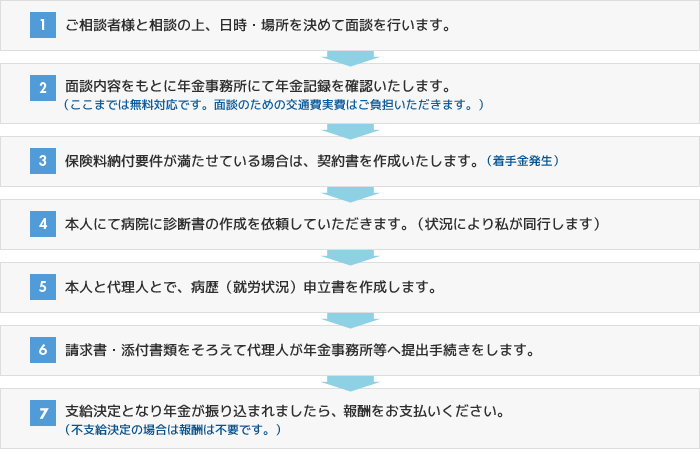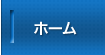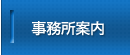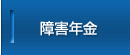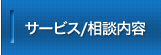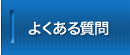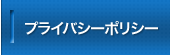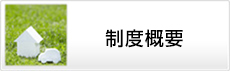障害年金とは年金加入中に傷病が発生し、一定の障害の状態になったときに、老齢年金の支給開始年齢に達するまでの期間、年金として支給されるものです。ほとんど全ての傷病が対象ですが、傷病の程度が定められた程度(障害認定基準)にあることが必要です。また、傷病が発生する前(初診日前)に保険料の滞納が多い(原則3分の1以上)と支給されません。なお、20歳前に初診の場合は保険料納付の要件はありません。また、老齢年金の支給開始後はいずれか一方の年金を選択することになります。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいい、具体的には以下のように取り扱われています。

- ①初めて診療を受けた日
- ②同一傷病で病院が変わった場合は、一番初めに診療を受けた日
- ③誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
- ④障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
例 糖尿病と糖尿病性網膜症等
| 1級 | 他人の介助を受けなければほとんど日常生活ができない程度の病状 身体の状況が病室内(又は自宅の病床室内)に限られるような状態 |
|---|---|
| 2級 | 日常生活に著しい制限が必要な程度の病状 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが 日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることが難しい程度の状態 (人工透析は2級とされています) |
| 3級 | 労働に著しい制限が必要とする程度の病状 日常生活は概ね支障がないが労働には著しい制限が伴うような状態 (心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門は3級とされています) |
- ※上記は、ほんの一例であり、障害等級は障害認定基準に基づき認定されます。

障害年金の請求に対して行われる決定内容に不満がある場合は、不服申立てができます。不服申し立ては2審制になっていて、1回目の不服申立ては地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。その社会保険審査官の決定に不服がある場合は、2回目の不服申立てとして社会保険審査会に再審査請求ができます。なお、社会保険審査会の裁決例の一部は下記URLでご覧になれます。
- ①障害認定日請求(初診日から1年6ヶ月の時に請求する場合)
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月時点)以後3ヶ月の病状を記載した診断書
障害認定日から1年以上経過して請求する場合は請求日現在の診断書も必要です - ②事後重症請求
(初診日から1年6か月当時の病状は軽かったが、その後悪化し、障害等級に該当する場合) - 請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書
- ③診断書記載の医療機関(病院等)以前にも受診した医療機関がある場合
- 上記のほかに受診状況等証明書(初診の証明)が必要です。
| メリットその1 | 障害年金の制度を熟知しているため、「通りやすい」書類の整備が迅速かつ正確に行われます。 |
|---|---|
| メリットその2 | 審査結果に不服がある場合の不服申立ても、社会保険労務士が代理で手続きを行うことができ、 当初の請求から不服申立てまで一連の手続きを任せることができます。 |